「四毒」という言葉をご存知でしょうか。吉野敏明先生が提唱し、主に甘いもの、小麦、乳製品、油を避けるべきものとして、健康界隈で急速に広がりを見せています。しかし、神戸の中村篤史医師は、ご自身のブログで「四毒の嘘」という衝撃的なタイトルを掲げています。このタイトルだけを見ると、中村医師が「四毒抜き」を全面的に否定しているように思えますが、その真意を徹底解説すると、中村医師が考える「毒」と「そうでないもの」の基準は、単なる否定ではないことがわかります。
本記事では、この「四毒の嘘」というタイトルの裏にある中村医師の考え方、すなわち粗悪品を否定する考え方に焦点を当てます。中村医師が、従来の指導内容には新味がないとしつつも、なぜ「四毒」という言葉に違和感を覚えるのか、そして、健康な人や不調がある人への四毒抜きアドバイスはどのように違うのかを深掘りします。
さらに、北海道の自然食品店まほろばと共通する考え方や、製粉所職員が語る小麦の毒性の真実、牛乳が体に悪いのではない、加熱殺菌が問題であるという独自の知見についても詳しく解説していきます。
この記事のポイント
- 中村医師が「四毒の嘘」というタイトルをつけた背景と、その真の意図は、吉野先生の主張全体を否定するものではないこと
- 中村医師が考える「毒」とは、本来の食材そのものではなく、品種改良、農薬、加熱殺菌などの「不自然な加工や環境」にあるという基準
- 健康状態によって「四毒抜き」の必要性が異なり、不調のある人は最低3ヵ月は徹底して抜く必要があるという吉野先生のアドバイス
- 中村医師の考え方が、北海道の自然食品店まほろばと「粗悪品を避けて良質なものを選ぶ」という点で共通していること
中村篤史医師の「四毒の嘘」とは?真意を徹底解説
「四毒」という言葉の広がりと中村医師の認識
中村篤史医師は、患者さんから「四毒」という言葉を聞くまでその存在を知りませんでした。数か月前に初めて患者さんから「甘いもの、小麦、乳製品、油」を指す言葉として聞き、それが吉野敏明先生によって広まっていると知ったそうです。その後もちょくちょく他の患者さんから聞く機会があったため、この言葉が界隈で広く浸透していることを認識しています。しかし、中村医師が以前から患者さんに伝えてきた「甘いもの、小麦、乳製品は控えめに」という指導内容自体には特に新味はないと考えています。一方で、「油」については、サラダ油や粗悪な安価なオリーブオイルなどを避けるようにとは指導してきましたが、油全般を忌避する指導はしていなかったとのこと。なぜなら、炒め物などで適量使う分には問題ないという認識だったからです。これが、「四毒」という言葉が一般化したことにより、中村医師としては「四毒、避けてますか」と聞き洩らしなく問える便利な言葉だと捉えつつも、ご自身から積極的にこの言葉を使うことは控えている状況です。なぜならば、現状ではまだこの言葉を知らない患者さんのほうが多いからです。しかしながら、健康意識の高まりから、すでに「小麦はよくない」と控えめにしている患者さんが増えており、指導の手間が省けているというメリットも感じています。
吉野敏明先生の「四毒」と中村医師のブログタイトル
中村篤史医師は、ご自身のブログで「四毒の嘘」というタイトルを公開していますが、これは吉野敏明先生の著書『四毒抜きのすすめ』を執筆時点で読んでいないと白状しています。このタイトルは、患者さんから「四毒」という言葉をちょくちょく聞くようになったことがきっかけとなってつけられたものです。多くの医師は、「歯科医師ごときが”うけ狙い”で言っている」という感覚を持っているかもしれませんし、メンタリストDaiGo氏も当初はそのような感覚で、論文を根拠に「四毒抜きは嘘」と動画で投稿した経緯があります。しかしながら、吉野先生は論文を執筆する側の人間であり、論文がいかに恣意的に作成され得るかという点についてメンタリストDaiGo氏へ反論のメッセージを発信しています。吉野先生の一連の話を聞くと、健康な人はそこまで熱心に四毒抜きをする必要はないものの、すでに何らかの身体的なトラブルが生じている場合、最低3ヵ月はスパッと抜く必要があるというのがその真意です。中村医師は、吉野先生の言葉が広がることで、一般大衆の問題意識を喚起するうえで「毒」という強烈な表現がキャッチーで効果的であることは理解しつつも、食品のすべてを一律に「毒」として遠ざける考え方には、専門家として慎重な立場を取っています。
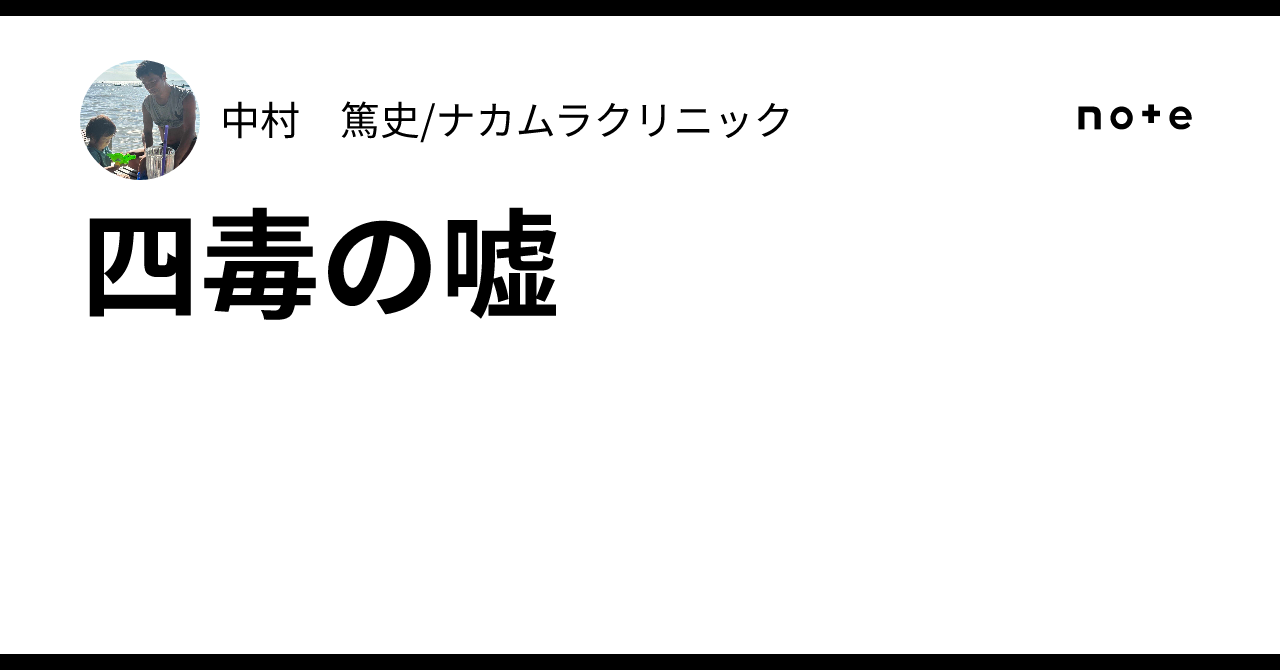
中村医師が考える「毒」と「そうでないもの」の基準
中村篤史医師は、「四毒」と称される甘いもの、小麦、乳製品のすべてが本来的に毒ではないと考えています。中村医師の考える「毒」と「そうでないもの」の基準は、自然であるか、不自然な加工や環境にあるかにあります。たとえば、甘いものに関しては、グルコースは生存に必須であり、語源的にも「あまいもの」は「うまいもの」であるため、すべてが毒ではありません。ただし、精製過程で栄養が空っぽになり、代謝でビタミン・ミネラルを消耗し、血糖値が急上昇する白砂糖はお勧めしません。代わりに黒砂糖や蜂蜜、さらに良いのは季節の果物や甘酒、サツマイモなどで甘いもの欲求を満たすことを推奨しています。小麦についても、グルテン不耐症の問題があるというより、現代の品種改良されたパンコムギ自体が問題であり、有機無農薬であってもブレインフォッグなどの症状が出ると考えています。しかし、100年前の原種であるスペルトコムギであれば問題がないという実験結果から、品種自体に問題があると指摘しています。乳製品についても、本来は毒ではありませんが、ホルモン剤、抗生剤、遺伝子組み換え飼料、劣悪な飼育環境で育った牛のミルクは汚れており、体に悪いと見ています。さらに、牛乳は日本国内で加熱殺菌が義務付けられていますが、加熱によって酵素が失活することが問題であり、非加熱の生乳であれば疾患の改善効果があるという臨床的知見も紹介しています。つまり、食材に罪はなく、妙な品種改良や加工、不自然な飼育環境によって「毒」になってしまうというのが、中村医師の基準です。
北海道の自然食品店まほろばと共通する考え方
中村篤史医師の「四毒の嘘」という一見過激なタイトルのブログも、その真意を読み解くと、北海道にある自然食品店まほろばさんの提唱する考え方と、本質的な部分で深く共通していることがわかります。この共通点は、すべてを否定するのではなく、粗悪なものと高品質なものを厳密に区別するという点に集約されます。まほろばの宮下ご夫妻は、マクロビオテックの桜沢如一先生の弟子筋にあたり、自然で質の高い食を長年推奨してきました。言ってしまえば、中村医師が「毒」とみなしているのは、遺伝子組み換えや農薬、過剰な加工によって不自然なものになってしまった小麦・植物油・牛乳・甘い物であり、本来の自然な食品ではありません。例えば、前述の通り、牛乳は劣悪な飼育環境や加熱殺菌が問題であり、小麦は品種改良や残留農薬が問題であるという論理です。本来は、食材自体に罪はないという考えに基づいています。このような考え方から、健康な人が食生活を送る上で、中村医師や、まほろばさんが厳選して推奨している商品の中から選んでいれば、食の安全と健康維持において大きな間違いはないという結論になります。つまり、単なる「四毒抜き」という制限ではなく、「良質なものを選ぶ」という積極的な行動こそが、両者に共通する健康哲学であると言えるでしょう。
健康な人・不調がある人への四毒抜きアドバイス
吉野敏明先生の提唱する「四毒抜き」は、その実施の必要性が議論の的となっています。吉野先生の真意は、人々の健康状態に応じて、四毒を避けるべきか否かを分けるべきという、非常に現実的なアドバイスです。このため、現在、特に自覚症状もなく健康であると感じている人は、そこまで神経質になって四毒を熱心にスパッと抜く必要はありません。もちろん、食の質を高める努力は推奨されますが、過度な制限は精神的な負担となり得ます。一方、もしあなたがすでに何らかの身体的なトラブルや慢性的な不調を抱えている場合は、この四毒が原因となっている可能性を排除する必要があります。これらの理由から、吉野先生は、不調がある人に対しては、最低でも3ヵ月間は四毒を完全に抜くことを強く推奨しています。これは、体内の炎症やアレルギー反応を誘発する可能性のある食品を一時的に完全に排除することで、身体の回復力を最大限に引き出し、原因を特定するための重要な「試験期間」であると理解すべきでしょう。しかし、デメリットや注意点として、長期間の極端な制限は栄養バランスの偏りや社会生活上のストレスとなる可能性もあるため、体調が改善した後は、前述の通り、中村医師や自然食品店が推奨するような質の高い食品を、柔軟に取り入れていくことが現実的です。
中村篤史の「四毒の嘘」は粗悪品を否定する考え方
甘いものは必要!白砂糖と黒砂糖・蜂蜜・果物の違い
中村篤史医師は、人工甘味料のような不自然なものを除き、甘いものは私たち人間の身体と本能にとって必要なエネルギー源であると述べています。その理由は、グルコース、すなわちブドウ糖が生命維持に必須なエネルギー源であり、「あまいもの」という言葉が「うまいもの」から派生したように、私たちの生存本能に根差した感覚だからです。いくら健康志向が高まっているからといって、極端な糖質制限によりグルコースの供給が断たれると、体はタンパク質や脂質からわざわざグルコースを糖新生という形で作り出すほど、それを必要としています。
しかし、ここで注意すべきデメリットは、精製過程で栄養が空っぽな上に、代謝でビタミン・ミネラルを消耗し、急激な血糖値の上昇を引き起こす白砂糖を摂りすぎることです。中村医師は、白砂糖ほどの負担がかからない黒砂糖や蜂蜜を代替品として推奨していますが、一方で、吉野敏明先生の考える「四毒抜き」では、白砂糖だけでなく、血糖値を急上昇させるすべての食品を避けるようにアドバイスされています。これには、中村医師が推奨する黒砂糖・はちみつ・フルーツや野菜の一部も含まれます。ただし、吉野先生は糖新生が起こらないよう、お米はしっかりとるように指導しています。
さらに、北海道の自然食品店まほろばさんでは、本来無色透明な糖蜜が酸化してできた黒砂糖は、有害ミネラルを含む商品が多く、かえって白砂糖より害のある商品が多いと警告しています。そのため、「どうせ摂るなら」という理由で、独自にオリジナル甘味料「一二三糖(ひふみとう)」をまほろば独自の知見として開発しました。このように、同じ「甘いもの」というカテゴリであっても、医師や専門家によって、その良し悪しの判断や推奨される代替品が異なるため、どの情報に基づいて食を選択するかが重要となります。
「毒」となる小麦は品種改良されたパンコムギか
中村篤史医師は、現代で一般的に流通している小麦、特に品種改良された「パンコムギ」が、健康上の問題を引き起こす主な原因であると考えています。小麦が体に悪いとされる理由について、多くはグルテンの問題に焦点が当てられますが、中村医師が紹介している書籍『小麦は食べるな』の著者の実験結果は、異なる視点を提供しています。この著者は、有機無農薬のパンコムギで作ったパンを食べた際、思考力が低下する「ブレインフォッグ」の症状が出たことを報告しています。このことから、いくら栽培方法が良くても、パンコムギという品種自体がすでに問題を抱えている可能性が示唆されます。そのため、小麦を避けることは、必ずしもグルテン不耐症であることだけが理由ではないのかもしれません。そして、この品種改良された小麦には、さらに複数の問題が重なっています。製粉会社に勤める職員からの情報によると、仕入れられた小麦には、収穫前に散布される残留除草剤が大量に含まれているだけでなく、海外からの輸入船内での殺虫剤、そして製粉所での臭化メチルによる燻蒸という、多くの毒物がしみこんでいる状態です。言ってしまえば、これだけの毒物を体内に取り込むことになれば、病気にならない方が不思議であるという指摘です。このような理由から、農薬や化学肥料、そして不自然な加工を経たパンコムギを、中村医師は「毒」とみなしているのです。
スペルトコムギなら問題なし?グルテン不耐症の真実
中村篤史医師が紹介する研究結果や知見によると、小麦に含まれる成分に対する不耐症を持つ人でも、「スペルトコムギ」であれば問題なく食べられる可能性があります。スペルトコムギとは、約100年前のヨーロッパ人が食べていた小麦の原種に近い品種です。前述の通り、現代の品種であるパンコムギを使ったパンを食べると体調不良やブレインフォッグを経験した著者が、スペルトコムギの小麦粉を使ってパンを作り食べたところ、体調に何の影響も出なかったという実験結果があります。これは、その著者が正確な意味でのグルテン不耐症ではないことを示唆しています。なぜならば、スペルトコムギにもグルテンは含まれているからです。このことから、多くの人が「小麦をやめたら体調が良くなった」と感じていても、実はグルテンそのものが原因ではなく、現代のパンコムギに含まれる何らかの成分に対する不耐症だった可能性があるのです。つまり、スペルトコムギのパンや麺であれば、本来は食べても問題なかったかもしれません。しかし、注意点として、スペルトコムギは現代のパンコムギに比べて少し価格が高いというデメリットがあります。にもかかわらず、健康を考慮すれば、パンコムギに含まれる過剰な農薬や品種改良による不自然な成分を避けることができるため、「毒」とならない小麦を選ぶという選択肢を提供してくれる品種であると言えます。
牛乳が体に悪いのではない、加熱殺菌が問題
中村篤史医師は、本来、牛乳が体に悪いわけではないと考えており、その問題の根源は「加熱殺菌」にあると強く主張しています。しかし、この加熱殺菌の問題以前に、現代の牛乳は、牛の飼育環境自体に大きな問題を抱えています。これは、母牛にホルモン剤を投与して不自然にミルクを出し続けさせ、それによって生じる病気に対して抗生剤やワクチンが投与されているという事実です。また、牛が食べる飼料も遺伝子組み換えである場合が多く、劣悪な環境で飼育されています。このような不自然な飼育環境にある牛の血液が汚れているとすれば、血液が濾過されてできる牛乳も当然汚れており、体に良いわけがないという見解は以前から持っていました。しかし、さらに重要だと中村医師が確信したのは、酵素に関する著書『酵素の力』を読んでからです。この本では、非加熱の生乳を飲むことで様々な疾患が改善する一方、加熱殺菌した牛乳では体調不良が見られたという研究結果が多数紹介されています。例えば、加熱ミルクを用いた動物実験において、成長への著しい影響が観察されたという報告や、加熱殺菌で酵素が壊れることが母乳と粉ミルクの決定的な違いであるという指摘です。加熱は食材のビタミンや酵素を破壊し、消化を大変にするというデメリットをもたらします。そのため、牛乳が毒なのではなく、加熱によって酵素が失活した牛乳が問題であるという考えに至ったのです。ただし、日本では牛乳の加熱殺菌が義務付けられているため、一般のスーパーで非加熱の牛乳を手に入れることができないという注意点があります。
牛乳の酵素と加熱による影響についての臨床的知見
中村篤史医師は、生乳に含まれる酵素が、加熱殺菌された牛乳との決定的な違いであり、健康への影響を分ける要因であると考えています。結論として、加熱殺菌によって酵素が失活することが、牛乳を体に悪いものに変えてしまうという臨床的な知見が存在します。これは、生ものにはそれ自身の酵素が含まれており、それによって消化吸収の負担がほとんどないのに対し、火を通すと酵素が壊れるため、人間の側で消化酵素を頑張って産生しなければならず、消化に大きな負担がかかるというメカニズムに基づいています。このため、現代人の疾患の大半は、加熱食の食べすぎ、あるいは酵素の摂取量が少なすぎることから来ているという主張もあります。実際、生牛乳と殺菌牛乳を飲んだ子どもを対象とした研究では、精製炭水化物の多い食事にもかかわらず、生牛乳を飲んでいた子どもには虫歯が一人もいなかったという報告があります。また、未熟児に生乳を与えたグループは順調に成長したのに対し、高温で加熱したミルクを与えたグループでは成長低下や下痢などの体調不良が見られました。さらに他の動物実験では、ネズミに加熱温度を上げた牛乳を与えたところ、加熱温度が高いほど短期間で全滅するという驚くべき結果が出ています。このような臨床的な観察や実験データから、中村医師は「牛乳自体の問題以上に、加熱工程が成分の質に与える影響が重要である」との見解を示しています。酵素は、ビタミンと同様に熱に弱く、加熱によってその力が失われることが、多くの体調不良の原因となっている可能性があるのです。
製粉所職員が語る小麦の毒性:農薬と燻蒸の真実
製粉所に長年勤務する職員の方からの生々しい証言は、中村篤史医師の「四毒」に関する見解、特に小麦の問題を裏付ける最も具体的かつ深刻な理由を提供しています。結論として、その職員は「小麦は食べません」と断言しており、これは輸入・保管・加工の過程で、大量の農薬と燻蒸剤が使用されているためです。職員が働き出した20年前と比較しても、最近の状況はさらにひどくなっているといいます。主な理由として、収穫前に除草剤を散布し、枯れさせてから収穫する手法が一般化しており、残留除草剤の量が尋常ではないことが挙げられます。さらに、海外からの輸入船の中でも殺虫剤が散布され、製粉所に仕入れてからも、虫を殺すために臭化メチルを充満させて燻蒸・保存しています。その職員は、この臭化メチルによる化学的な刺激が、近年多くの人が訴える環境過敏な体調不良の感覚と通じるものがある、と警鐘を鳴らしています。また、実際に小麦粉を作る会社に勤めているからこそ、仕入れた小麦には殺虫剤、除草剤、虫、異物が大量に含まれているという内情を知っているため、安心して食べることができないのです。国産小麦のほうがまだマシなようですが、輸入もの、特にアメリカ産やカナダ産はひどく、大手に卸されてケーキや麺になっているという現状があります。この職員は実践的なアドバイスとして、農薬がかたまりやすい全粒粉や胚芽を含んだ「ふすま粉」は絶対に食べないほうがよいと述べています。グルテンの問題などよりも、農薬、化学肥料、除草剤、殺虫剤、そして燻蒸というこれだけの毒物をしみこませた小麦は、本来の「食材」としての純粋さを失っている可能性があるという、現場からの切実な指摘です。
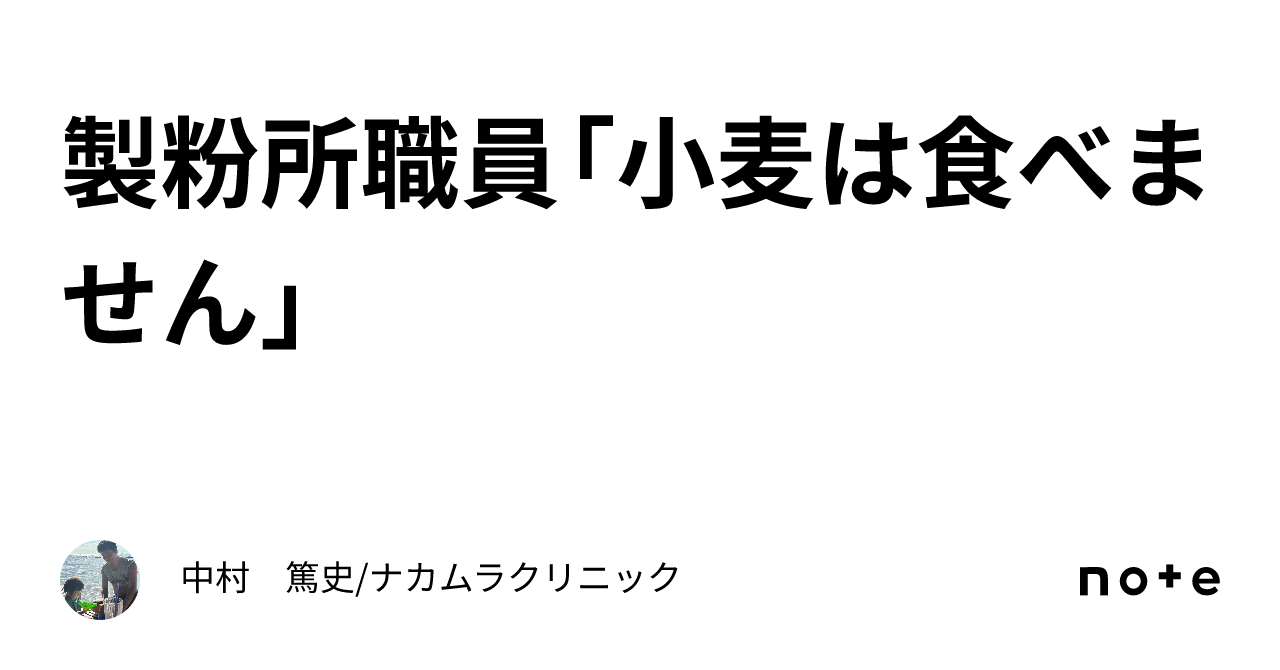
中村篤史医師が語る「四毒の嘘」とは何か、その真意の総括
- 中村医師は「四毒」という言葉を患者から聞いて存在を知り、吉野敏明先生によって広まったと認識
- 従来の「甘いもの、小麦、乳製品控えめ」という指導と内容に新味はない
- 「四毒」という言葉は患者への聞き洩らしがない便利なワードだと捉えている
- ブログタイトルは「四毒の嘘」だが、中身は高品質なもの以外を毒と見なす考え方
- 多くの医師は吉野先生の「四毒」をうけ狙いと見る感覚に近いと推測される
- 吉野先生は、不調がある人には最低3ヵ月は四毒を完全に抜くよう推奨している
- 中村医師は、食材のすべてを「毒」と表現することには違和感を覚えている
- 中村医師の基準は、自然であるか、不自然な加工や環境にあるかという点
- 小麦は現代の品種改良されたパンコムギ自体や、農薬・燻蒸剤の使用が問題
- 乳製品は劣悪な飼育環境や、加熱殺菌によって酵素が失活することが問題
- 甘いものは必要だが、精製された白砂糖ではなく、質の高い自然の甘さを推奨
- 北海道の自然食品店まほろばと、粗悪品を避けるという点で考え方が共通している
- 吉野先生は、白砂糖だけでなく血糖値を急上昇させる食品の多くをNGとしている
- まほろばは、通常の黒砂糖に有害ミネラルが多いとしてオリジナル甘味料を開発
- 製粉所職員の証言から、農薬・殺虫剤・燻蒸剤により小麦が毒物と化している実態が判明
- スペルトコムギのような原種であれば、グルテン不耐症でも問題ない可能性がある
あわせて読みたい
>>メンタリストDaiGoが語る「四毒抜きは嘘」vs 吉野敏明
>>船瀬俊介氏 「何が 四毒 だよ、バカ」その真意とは?





