塩が健康に悪くないと聞いて、本当にそうなのかと疑問に感じていませんか?
「塩は四毒ではない?」という言葉を目にして、何が正しいのかわからなくなっているかもしれませんね。
この記事では、塩分過多は高血圧や腎臓病の原因?といった一般的な疑問から、「塩は四毒ではない」真の理由、そして腎臓を傷つける植物性の油の害という意外な真実まで、深く掘り下げていきます。
この記事を読むことで、健康な腎臓であれば塩分排出は可能なことや、腎臓病患者の塩分摂取方法とはといった具体的な対処法が分かります。
また、にがりや植物油と四毒の関係から考える塩の選び方、にがりの凝固作用が健康に与える害、そして良い塩の選び方と製造方法についても解説します。
記事の後半では、筆者が長年使用しているおすすめの塩や、熊谷真実のまみちゃんねるコメントまとめから読み取れる視聴者の反応を紹介します。
そして最後に、「ダムが決壊する前」に気を付けること、塩と植物油との向き合い方を通じて、健康的な食生活を送るためのヒントをお伝えします。
この情報が、あなたの食生活を見直すきっかけになれば幸いです。
この記事のポイント
- 一般的な塩分過多と、四毒との関連性における高血圧や腎臓病の原因の違い
- 植物性の油が腎臓の毛細血管に与える具体的な害について
- 天然塩に含まれる「にがり」の凝固作用と、その健康への影響
- 健康を保つために、塩分よりも先に植物性の油を制限すべき理由
よしりん流・四毒理論から考える塩と高血圧の関係
塩分過多は高血圧や腎臓病の原因?
塩分の摂りすぎは、一般的に高血圧や腎臓病の原因になると考えられています。
これは、体内の塩分濃度を一定に保つために、余分な塩分を尿として排出する腎臓の働きが関係しているためです。
塩分を多く摂ると、その濃度を薄めようとして体内に水分が溜まり、血液の量が増えてしまいます。
その結果、血管にかかる圧力が高くなり、高血圧になるという仕組みです。
高血圧の状態が続くと、腎臓の毛細血管にも負担がかかり、ろ過機能が徐々に低下していきます。
腎臓の働きが悪くなると、さらに塩分や水分を排出できなくなり、血圧がさらに上昇するという悪循環に陥ってしまうのです。
このような理由から、長年にわたって塩分過多の食生活を送っていると、高血圧や腎臓病のリスクが高まると言われているわけです。
「塩は四毒ではない」真の理由
多くの人が高血圧や腎臓病の主犯は塩であると考えていますが、四毒の理論から見れば、視点は少し異なります。
塩そのものは、生命維持に不可欠なミネラルであり、健康な状態であれば過剰に摂取しても体は適切に排出します。
しかし、ある特定のものが原因で、腎臓がその排出能力を失うと、塩分過多が問題となるのです。
その真の原因とは、四毒の一つである植物性の油です。植物性の油を過剰に摂取すると、体内で酸化して血管を傷つけ、動脈硬化を引き起こします。腎臓は毛細血管の塊でできているため、この動脈硬化が特に影響を及ぼしやすい部分です。
血管が傷つき詰まってしまうことで、腎臓のろ過機能が低下し、本来排出できるはずの塩分や老廃物が体内に溜まってしまうのです。
つまり、塩分が直接的な原因ではなく、腎臓の働きを悪くする別の要因が存在するというわけです。
腎臓を傷つける植物性の油の害
植物性の油を過剰に摂取すると、さまざまな健康リスクが生じます。
体内で酸化した油は、動脈硬化を引き起こすだけでなく、血管に穴を開けることもあります。
すると、血管を修復しようと血小板が集まり、血管内がカサブタのようなもので覆われてしまいます。これが動脈硬化の正体です。
植物性の油の過剰摂取は、主に外食や加工食品、スーパーのお惣菜などを通じて起こります。
例えば、スーパーで売られている焼き魚は、見た目では油を使っていないように見えますが、実際には調理の際に油が塗られていることがほとんどです。
健康な腎臓であれば、ある程度の塩分は問題なく排出できますが、植物性の油によって腎臓が傷つき、機能が低下した状態ではそうはいきません。
そのため、腎臓の健康を保つためには、塩分よりも先に植物性の油の摂取量を見直すことが重要と言えるでしょう。
健康な腎臓なら塩分排出は可能
健康な腎臓は、体内の塩分濃度を常に最適な状態に保つように働いています。
食事から塩分を多めに摂取した場合でも、健康な腎臓は余分な塩分を尿として排出する能力を持っています。
そのため、腎臓の機能が正常であれば、日々の食生活で少し塩分を多く摂ったとしても、それがただちに高血圧や腎臓病につながるわけではないのです。
これは、植物性の油などによって腎臓がダメージを受けていないことが前提となります。
いくら良質な塩分であっても、腎臓自体が弱っていると、その排出機能は低下してしまいます。
本来、私たちの体は、健康な状態を維持するために自律的な調整機能を持っているのです。
腎臓病患者の塩分摂取方法とは
腎臓病を患っている方にとっては、塩分の摂取方法に細心の注意を払う必要があります。既に腎臓の機能が低下しているため、健康な人と同じように塩分を排出することはできません。
したがって、塩分摂取量を厳しく制限する必要が出てきます。具体的な摂取量は個々の病状によって異なりますが、一般的には一日5g以下、場合によっては3g程度にまで抑える必要があるといわれています。
これは、ミネラルが豊富な天然塩であっても例外ではありません。
なぜなら、この段階では塩の種類よりも、体内に溜まる塩分そのものが問題となるからです。
また、塩分だけでなく、腎臓に負担をかけるタンパク質の摂取量も制限する必要が出てきます。
一度腎臓が悪くなってしまうと、その機能が完全に元に戻ることは難しいため、病気になる前に予防することが最も重要です。
それでも病気になってしまった場合は、医師の指導に従い、徹底した食事管理を行うことが必須となります。
にがりや植物油と四毒の関係から考える塩
にがりの凝固作用が健康に与える害
一般的に「天然塩」や「自然塩」が良いとされ、その特徴である「にがり」の存在が注目されることがあります。
にがりはミネラルが豊富で健康に良いイメージがあるかもしれません。
しかし、にがりにはタンパク質を凝固させる作用があります。
この作用は、豆腐を作る際には不可欠なものですが、体内で直接摂取した場合、別の影響を及ぼす可能性があります。
特に、腎臓は毛細血管の塊でできており、非常に繊細な組織です。
にがりのタンパク質凝固作用が、繊細な腎臓の組織に影響を与える可能性が懸念されています。
腎臓のろ過機能は、まるで細かいふるいのような糸球体で行われていますが、これが硬くなると、老廃物を適切にろ過できなくなってしまいます。
古代の日本人が、海水を直接飲むと腎炎を起こして死に至ることを経験的に知っており、塩からにがりを分離する「枯らし」という工程を行っていたのは、このにがりの害を避けるための知恵だったと言われています。
つまり、天然塩だからといって無条件に良いわけではなく、その性質を理解した上で選ぶことが大切なのです。
良い塩の選び方と製造方法
良い塩を選ぶ際には、にがりの凝固作用が健康に与える影響を理解しておくことが大切です。
海水から作られる天然塩や自然塩の中には、このにがり分が多く含まれているものがあります。
かつて日本では、塩をかますに入れて水分を切り、にがり分を分離させる「枯らし」という伝統的な製造方法がありました。
これは、にがりの人体への影響を経験的に知っていた先人の知恵だったと言えるでしょう。
現代でも、にがり分を遠心分離機などで限界まで落とした塩や、にがり分がほとんどない岩塩などが存在します。
こうした製造工程を経た塩は、健康への配慮がなされており、安心して使える選択肢の一つです。
また、さまざまな塩をブレンドし、それぞれの良い点を生かしたオリジナルの塩も登場しています。
塩を選ぶ際には、単に天然かどうかに注目するだけでなく、その製造方法やにがり分の含有量にまで目を向けることが重要です。
柴又の鍼灸接骨院の院長に紹介され「塩は体に悪い」という常識を変えさせられた本↓
筆者が長年使用しているおすすめの塩
真生塩
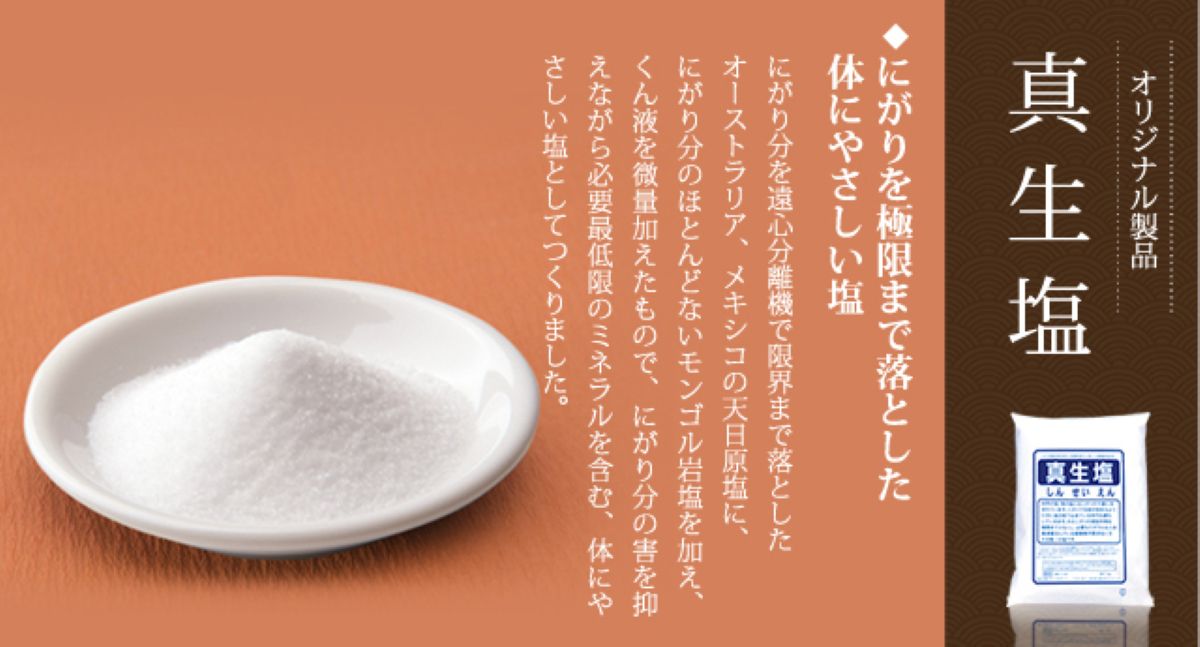
真生塩は、にがりの害を抑えながら、体にやさしく作られている塩です。天然塩に含まれるにがりには、タンパク質を硬化させる性質があるため、内臓に負担をかける可能性があります。
これを防ぐため、真生塩はオーストラリアやメキシコの天日原塩と、にがり分の少ないモンゴル岩塩をブレンドし、さらににがり分を遠心分離機で極限まで取り除いています。
また、必要最低限のミネラルは含まれているため、健康を意識しつつも、まろやかで使いやすい味わいが特徴です。
料理の味を引き立てるだけでなく、漬物や味噌作りにも適しています。
七五三(なごみ)塩
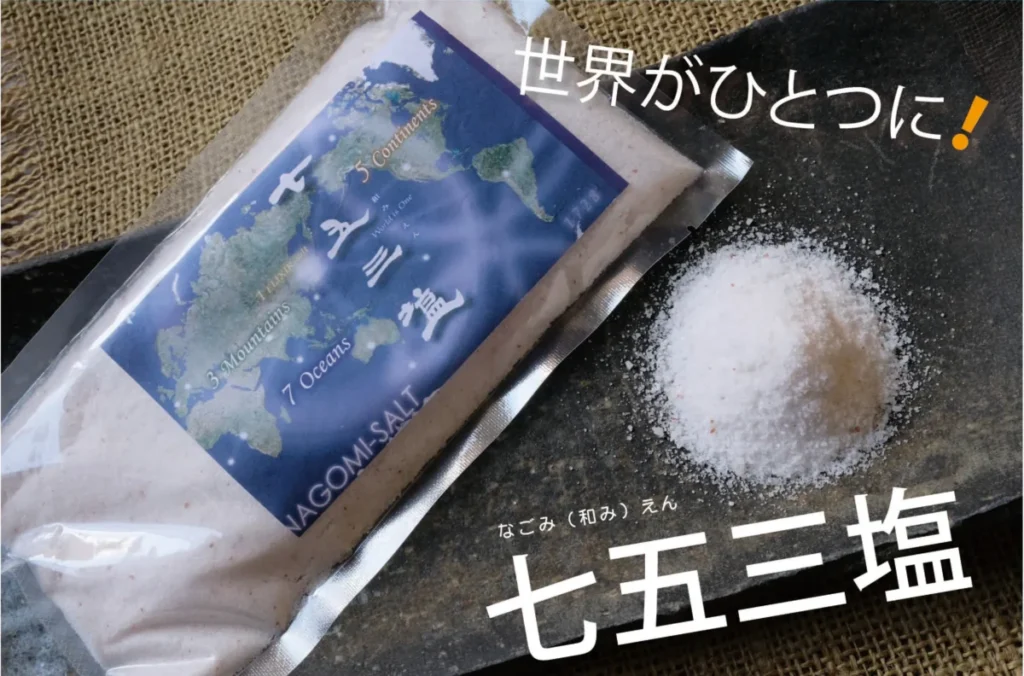
七五三塩は、世界中の塩を独自にブレンドしたエナジー・ソルトです。
北極海を含む七大海洋の海塩、五大州の湖塩、そしてヒマラヤ・アンデスなどの三大山脈の岩塩、さらにそれらを焼成した焼き塩など、20種類以上の塩を組み合わせて作られています。
この塩の大きな特徴は、単なるブレンドに留まらず、特殊なミキサーで1728回転という神秘的な数秘に基づいて攪拌されている点です。
これにより、複雑で奥深い味わいが生み出され、シンプルな塩焼きから煮物、隠し味まで、あらゆる料理に深みを与えます。
世界中の塩が調和し、豊かなエネルギーを感じられる、歴史的にも類を見ない特別な塩です。
熊谷真実のまみちゃんねるコメントまとめ
熊谷真実さんのYouTubeチャンネル「まみちゃんねる」には、塩と健康に関する貴重な情報交換がされています。
コメント欄には、視聴者の方々からの体験談や共感の声が多数寄せられています。特に目立つのは、「塩の摂りすぎが問題だと思っていたけれど、植物油の摂りすぎが問題だったとは初耳だった」という驚きの声です。
また、「塩を変えてから、スッキリした毎日を過ごせるようになった」「自分に合う感覚がある」といった、食生活の見直しによる前向きな変化を感じている声が多く見られます。
中には、「給食の揚げパンは四毒で固めたものだった」といった、具体的な食品に対する見方も変わったという意見もありました。
視聴者の方々が、この動画をきっかけに健康に対する意識を高め、自らの食生活を見直している様子が伝わってきます。
これらのコメントは、多くの人が健康的な食生活を模索していること、そして正しい情報が求められていることを示しています。
「ダムが決壊する前」に気を付けること

健康な体は、川の流れに例えるとスムーズに水が流れているダムのようなものです。
しかし、植物性の油やにがりといった体に負担をかける要因を長年にわたって蓄積していくと、少しずつダムにひびが入っていきます。
このひびが、病気の前兆となる体の不調です。しかし、多くの人は、この段階ではまだ自覚症状がないか、あっても軽いために「少しぐらいなら大丈夫だろう」と過信してしまいがちです。
しかし、一度ダムが決壊してしまうと、修復するのは非常に困難です。
これは、健康も同じで、病気になってからでは、元の健康な状態に戻すことは難しいでしょう。
例えば、集中治療室で生死をさまよった後、以前と同じような生活に戻れる人は多くありません。
私たちは、日々の小さな不調を見逃さず、大きな病気につながる「ダムが決壊する前」に食生活を見直すことが何よりも大切です。
まとめ:塩と植物油との向き合い方
これまでの話をまとめると、塩そのものが健康の直接的な悪者なのではありません。
塩は私たちの体に必須のミネラルであり、健康な腎臓があれば適切に排出されるものです。
しかし、四毒の一つである「植物性の油」を過剰に摂取すると、腎臓の毛細血管が傷つき、機能が低下してしまいます。
すると、本来なら問題なく排出されるはずの塩分が体内に溜まり、高血圧や腎臓病を引き起こす原因となってしまうのです。
したがって、健康を維持するためには、塩分を必要以上に減らすことよりも、まず植物性の油の摂取量を減らすことが大切です。
特に、外食や加工食品に含まれている植物性の油には注意が必要です。自分で料理をする際には、植物性の油の使用を控え、良質な塩を選ぶように心がけましょう。
また、天然塩に含まれる「にがり」の作用も考慮し、製造工程がしっかりしている塩を選ぶことが重要です。
塩との付き合い方を見直すことはもちろん大切ですが、まずは植物性の油との向き合い方から見直してみるのが良いかもしれません。
四毒との関連から考える「塩」の健康への影響
- 塩は生命維持に不可欠なミネラルである。
- 健康な腎臓は余分な塩分を尿として適切に排出する。
- 塩分過多が直接的な病気の原因ではない。
- 四毒の一つである植物性の油が腎臓の機能を低下させる。
- 植物性の油は体内で酸化し、血管を傷つけ動脈硬化を引き起こす。
- 腎臓の毛細血管が詰まることで、ろ過機能が低下する。
- 腎機能が低下した状態で塩分を摂りすぎると、高血圧や腎臓病につながる。
- 腎臓病患者は塩分摂取量を厳しく制限する必要がある。
- にがりにはタンパク質を凝固させる作用がある。
- にがり分が多い塩は、腎臓の組織を硬化させる可能性がある。
- 日本の伝統的な塩作りには、にがり分を分離する「枯らし」という工程があった。
- 製造過程で不純物やにがり分を極力除去した塩が良い。
- 外食や加工食品に含まれる植物性の油に注意すべきである。
- 健康な体は「ダムが決壊する前」の予防が大切である。
- 塩との付き合い方を見直すより、まず植物性の油の摂取量を減らすことが重要である。
*本記事は吉野敏明先生の理論に基づいた解説であり、特定の疾患の治療を保証するものではありません。持病のある方は医師にご相談ください
あわせて読みたい
>>多くの女性が実践!四毒抜きが美容の常識を変える



