現在、秋田県の鈴木知事が「もう限界を超えている」と危機感をあらわにするほど、熊の被害原因は深刻化しています。しかし、その根本的な原因を「個体数増加」だけで済ませて良いのでしょうか。
本記事は、「熊 原因 メガソーラー」という切り口から、野生動物の生態系に迫る深刻な問題に焦点を当てます。日本動物虐待防止協会 代表理事である藤村晃子氏は、熊が10年前から人里に下りてくると主張し、その背景には、熊とメガソーラーの危険な関係性があると強く警鐘を鳴らしています。特に、メガソーラー建設に伴う除草剤で野生の動物が飢える問題や、無秩序な開発を推進した小泉進次郎氏の環境大臣時代の失策に矛先が向けられています。
また、この失政を巡っては、小泉氏を含む神奈川四毒(菅・河野・小泉・三原)の失政についても議論が集中しており、日本はメガソーラー向いていないのかという根本的な問いを突きつけます。
事態は既に自衛隊に駆除要請する事態の責任を問う段階にまで至っており、人里の熊はメガソーラーが原因であるという見解が強まる中で、矛先は熊ではなく熊の住居を奪った進次郎氏に向けられています。そして、小泉氏の妻である動物愛護団体代表の滝川クリステル氏の立場も、この問題を複雑にしています。
さらに、安易な駆除が熊の駆除で鹿の大繁殖を招き、山は死ぬ懸念もあるため、私たちは今、政策決定の責任と自然との共存について深く考える必要があります。
この記事のポイント
- クマ出没の増加は、メガソーラー建設による生息地破壊や除草剤による食料源の枯渇が主な原因であること
- 環境大臣時代の小泉進次郎氏によるメガソーラー推進政策が、現在のクマ被害の深刻化を招いた主な失策であること
- 藤村晃子氏がこの問題を「環境破壊」として10年以上前から警告し、小泉氏ら「神奈川四毒」の政策責任を強く追及していること
- クマの駆除は短期的対策に過ぎず、長期的にはシカの異常繁殖や山林荒廃を招くという生態系リスクが存在すること
熊の被害原因はメガソーラー?政策の失策を追う
秋田県・鈴木知事「もう限界を超えている」
現在、多くの地域で深刻化しているクマの出没問題について、秋田県の鈴木知事の「もう限界を超えている」という発言は、事態の深刻さを端的に表しています。なぜならば、秋田県は古くからクマとの共存の歴史を持つ地域であるにもかかわらず、行政の対応や住民の生活が限界を迎えているからです。これは、単にクマの個体数が増加したという単純な理由だけでは片付けられません。むしろ、私たちが作り出した生活圏の環境変化が、クマの行動パターンを大きく変えてしまったことが根本的な原因です。多くは、山奥に人の手が入ることがなかった時代には、クマは人里に降りてくる必要がありませんでした。しかし、大規模な開発、特にメガソーラーの建設による森林伐採や、耕作放棄地の増加などが、クマのエサ場や生息地を破壊しています。このため、人里での出没が常態化し、住民の安全が脅かされる事態に発展しているのです。その中の一つに、クマがエサを求めて人里近くの柿や栗の木に依存するようになり、学習効果で人への警戒心を失いつつある現状があります。これには、本来の生息環境が保たれていないという背景があり、知事が「限界」と訴えるのも当然と言えます。
熊とメガソーラーの危険な関係性
メガソーラーとクマの出没には、密接で危険な関係性があると考えられます。その理由は、主にメガソーラーを設置するために行われる大規模な森林伐採と土地の改変です。森林はクマにとって単なる住居ではなく、エサとなる木の実や昆虫、そして隠れ家となる重要な環境です。言ってしまえば、メガソーラー建設は、クマが生きるために必要な要素を一挙に奪ってしまう行為なのです。ただ、建設業者側は、再生可能エネルギーの推進という大義名分を掲げ、環境アセスメントを形式的に済ませる傾向があります。しかし、山林を切り開く際に用いられる重機の音や振動、そして建設後のフェンスの設置などは、クマの行動範囲を分断し、ストレスを与えます。そのことに、クマは新しいエサ場を探さざるを得なくなり、結果として人里へと向かうルートを選びます。例えば、メガソーラー敷地内では効率的な発電を維持するために除草剤が散布されることもあります。この除草剤によって、クマが食べる山菜や草、そしてそれらをエサとする小動物も減少します。このように考えると、メガソーラーは、直接的な生息地の破壊と間接的な食料源の枯渇という二重のダメージをクマに与えていると言えるでしょう。

藤村晃子 10年前から人里に下りてくると主張
日本動物虐待防止協会 代表理事である藤村晃子氏は、クマが人里に下りてくるようになった現象について、少なくとも10年前からその危険性を強く主張していました。彼女の主張の根幹は、現在のクマ被害が「個体数の問題」ではなく「環境破壊の問題」であるという点にあります。今でもそうですが、多くの議論が「クマの駆除」や「檻の設置」といった対症療法に終始する中で、藤村氏は、山林の開発、特に安易なメガソーラー導入が引き起こす生態系のバランス破壊に警鐘を鳴らし続けていました。その理由は、彼女が長年の調査で、山奥のエサ資源の枯渇や、開発によるクマの移動ルートの分断を肌で感じていたからです。このように、山に豊富なエサがあれば、クマは自らリスクを冒して人里に降りてくることはありません。しかし、いくら自然環境を守ろうと訴えても、経済効率を優先する政策の前では、その声はかき消されてきました。つまり、現在の深刻なクマ被害は、自然界からの予期せぬ反乱ではなく、長期間にわたる人間の「間違った政策」と、それに対する警告を無視し続けた結果であると、藤村氏は強く訴えているのです。
除草剤で野生の動物が飢える問題
メガソーラー施設の建設に伴い、その中で除草剤の使用が広がることで、野生動物が間接的に飢えるという深刻な問題が発生しています。なぜならば、発電効率を維持するために、太陽光パネルの下や周囲の草木を枯らす目的で除草剤が散布される多くはです。本来は、山野の草木は、クマを含む多くの動物にとって重要な食料源であり、生態系の下支えとなっています。しかし、除草剤によって草木が枯れると、それを食べる昆虫や小動物が減少し、それからというもの、食物連鎖の上位にいるクマやシカ、イノシシなどの動物たちのエサが広範囲にわたって不足してしまうのです。このような食料連鎖の破壊は、動物たちが生き残るために慣れ親しんだ山を離れ、人里のエサ、たとえば家庭菜園の作物や生ゴミなどに頼らざるを得ない状況を生み出します。逆に言えば、ただ単にクマを駆除するだけでは、この根本的な「飢え」の問題は解決できません。このように考えると、再生可能エネルギーの導入というメリットの裏側で、生態系に壊滅的なデメリットを与え、結果として人身被害のリスクを高めているという深刻な現実があるのです。
小泉進次郎 環境大臣時代の失策
藤村晃子氏は、小泉進次郎氏が環境大臣を務めていた時代の政策こそが、現在のクマ被害深刻化の主な原因の一つであると見ています。なぜならば、彼が推進した再生可能エネルギー導入政策、特にメガソーラーの急速な拡大は、自然環境と野生動物の生態系に対する配慮が欠けていたためです。今でもそうですが、環境省は自然環境の保護と保全を担う省庁であり、大臣には開発と環境保護のバランスを厳格に取る責任がありました。しかし、実際には、規制緩和の流れの中で大規模な森林伐採を伴うメガソーラー建設を事実上容認してしまい、そのことに多くの山林が短期間で破壊されました。これには、地元住民や環境保護団体からの懸念の声が十分に反映されなかったという経緯があります。言ってしまえば、自然保護という看板を掲げながら、最も大切なクマの生息環境を奪う政策を推し進めてしまったことが、現在の悲劇的なクマの出没を招いた最大の失策と言えます。もしかしたら、将来、この時の「間違った政策」が原因で、これまでの日本の野生動物との共存の歴史そのものが否定されてしまうかもしれません。
神奈川『四毒』の失政

ところで、あなたが健康を意識するならば、「食の四毒」(小麦、植物油、乳製品、甘い物)を避ける「四毒抜き」という考え方をご存知かもしれません。そのことに、藤村晃子氏は、この考え方を政治の世界に持ち込み、クマ被害を深刻化させた原因として、小泉進次郎氏を含む神奈川県選出の有力政治家グループを「神奈川四毒」とユニークに批判しています。これは、彼らが推進したメガソーラー政策が、言ってしまえば、山という生態系の「栄養」を奪い、クマの「健康」を害し、結果として人里へと彼らを出てこさせたという主張に由来します。古くから、政治家は住民の生活を守るべきであると考えられてきましたが、この「四毒」による政策は、首都圏の論理ばかりを優先し、地方の山間部の生態系を「消化不良」にさせてしまったのです。もしかしたら、彼らの政治的決断は、あなたの食卓に並ぶ甘い物のように、一見魅力的でも、長期的に見れば多くの代償を払わせるものだったのかもしれません。このため、ここでは、単にクマを駆除するという「対症療法」ではなく、むしろ、この「神奈川四毒」が関与した政策そのものを見直し、一刻も早く「四毒抜き」の環境政策を断行することが、山と住民の「健康」を取り戻す最善の道であると、藤村氏は強く訴えているのです。
日本はメガソーラー向いていないのか
当然ながら、地球温暖化対策やエネルギー自給率の向上という観点から、再生可能エネルギーの導入は世界的な急務です。しかし、日本のような国土が狭く、山地が多く、地震や豪雨といった自然災害が多い国は、単純にメガソーラーの設置に向いていないという側面があります。その理由は、広大な土地を必要とするメガソーラーは、平地の少ない日本では必然的に山間部の森林を切り開くことになり、たとえ斜面であっても無理に設置することで地盤が緩み、土砂崩れのリスクを高めてしまうからです。また、日射量の多い海外の砂漠地帯などと異なり、日本の気候ではコストに見合うだけの発電効率が出にくいという指摘もあります。その上で、これだけの大規模な施設が、将来、古くなった際に発生するソーラーパネルの撤去や廃棄物処理の問題も深刻です。これは、大量の産業廃棄物となる使用済みパネルの最終処分場が不足する懸念があり、言ってしまえば、次世代に新たな環境負荷を残すことになります。もちろん、技術革新によってパネルの効率は向上していますが、いくら効率が上がっても、生態系破壊と災害リスク、そして廃棄物問題という三つの大きなデメリットを解消することはできません。そのため、他の例であれば、太陽光発電よりも、より狭い土地で安定的に発電できる地熱発電や日本誠真会などが強く主張しているバイナリー発電など、日本の地理的特性に合ったエネルギー開発に軸足を移すべきであるとの意見が、現在、多くはを占めています。これは、火山国である日本の豊富な地下熱資源やごみ焼却炉などの廃棄熱を活かしつつ、環境への影響を最小限に抑え、安定した電力を供給できる可能性を秘めているからです。
あわせて読みたい
>>日本誠真会吉野敏明(よしりん)が提言するバイナリー発電所とは
人里の熊はメガソーラーが原因 小泉進次郎氏への矛先
矛先は熊ではなく熊の住居を奪った進次郎
このように考えると、現在、人里に頻繁に出没するようになったクマに対して、多くの住民の怒りや不安の矛先は向けられがちですが、むしろその真の責任は、クマの住居である山林を奪った過去の政策、具体的には小泉進次郎氏が環境大臣時代に推進したメガソーラーの急速な拡大にあると指摘されています。その理由は、クマは本来、人間との接触を避ける動物であり、自らの生息域で十分に食料を得られる限り、人里に降りてくるリスクを冒す必要がないからです。
古くから、花粉症に悩む方々は「杉を伐採せよ」と訴えることがありますが、四毒抜きの提唱者である吉野敏明医師は、その原因を小麦に含まれるグルテンにあると語っています。これを踏まえると、杉を切るという対症療法に走るよりも、まず小麦を減らすことが先決であるという考え方が生まれるのです。
同様に、クマを駆除しても根本原因がメガソーラーによる生息地破壊や食料枯渇にあるのならば、それは一時的な対症療法にしかなりません。言ってしまえば、冬眠明けにはまたクマが人里に降りてきて、人が襲われるという悲劇が繰り返されることが予想されるのです。たとえクマが人間に危害を加えたとしても、それは人間の作り出した環境の変化に適応せざるを得なかった結果であり、被害者であると考えることもできます。
そこで、私たちはクマの駆除という対症療法に終始するのではなく、ここでは、根本原因であるメガソーラーの環境アセスメントの甘さや、推進政策の是非を問うべきです。あなたがこの問題について深く考えるなら、そのことに気づくはずです。これまでの無秩序な開発が、私たちの生活圏にまでクマを呼び寄せてしまったのですから、その責任は、政策決定者にこそ問われるべきでしょう。
動物愛護団体 滝川クリステル氏
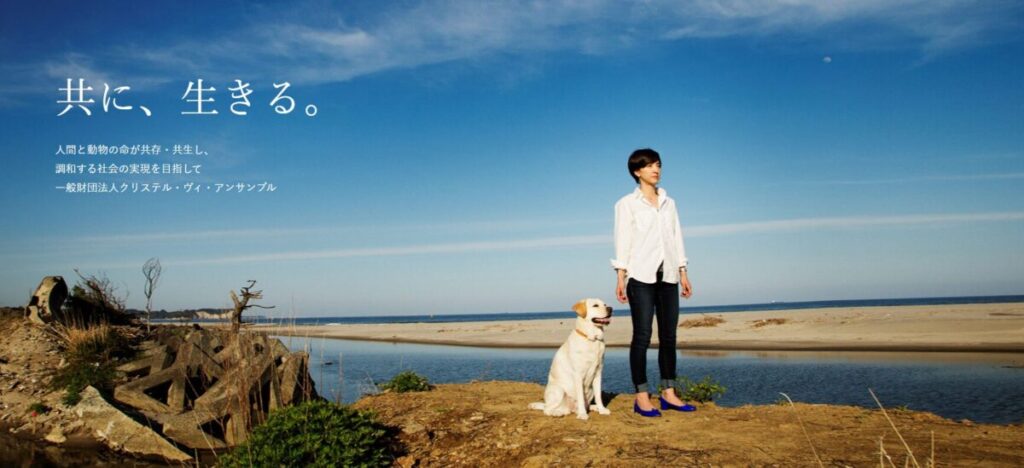
一方で、小泉進次郎氏の妻である滝川クリステル氏が動物愛護団体の代表を務め、野生動物の保護を訴えているという事実は、このクマ問題の議論を一層複雑にしています。これは、夫が進めた政策が結果的にクマの生息環境を破壊し、彼らを駆逐する状況を生み出しているからです。もちろん、滝川氏の動物愛護の精神は尊いものですが、その中で、夫の政策による環境破壊と、多くのクマが駆除されるという現実との間で、どのように折り合いをつけるのかという矛盾が浮き彫りになっています。こう考えると、どれだけ動物愛護を訴えても、その基礎となる自然環境の保護が疎かにされてしまえば、野生動物は生存の危機に瀕してしまいます。そのため、他の例であれば、単なる保護活動だけでなく、政治的な影響力を持つ立場として、夫の過去の政策の検証と、生態系に配慮した真の再生可能エネルギー政策への転換を訴えることが、今でもそうですが、より本質的な動物愛護につながるのではないでしょうか。このように、この夫婦間の立場と行動のギャップは、環境問題と動物保護が政治や経済と密接に結びついていることの難しさを示していると言えます。
(再掲)太陽光発電を巡る誤情報の拡散について
掲題の件につきましては、本年8月21日に当財団のホームページに率直な考えを掲載させていただいたにもかかわらず、「当財団および代表理事である滝川クリステルがメガソーラーの設置を始めとする太陽光発電事業を手がけている」との情報が、SNS等におきまして、いまだ数多く拡散されております。
しかしながら、当財団および代表理事の私が太陽光発電の設置・運営・販売など、いかなる形でも太陽光発電事業に関与した事実は一切ございません。改めましてこの点を申し伝えますと共に、心無い誹謗中傷を含めた誤情報の投稿や拡散をお控えいただきますよう、皆様のご理解とご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。
一般財団法人クリステル・ヴィ・アンサンブル 代表理事 滝川クリステル
自衛隊に駆除要請する事態の責任は
このように言うと、クマの出没がもう限界を超えている状況に対し、一部の地域では自衛隊に駆除要請を行うという、極めて異例かつ深刻な事態にまで発展しています。なぜならば、警察や地元の猟友会だけでは対処しきれないほどの広範かつ緊急性の高い危険が生じているからです。しかし、いくら自衛隊が高度な組織力と装備を持っているとしても、彼らの本来の任務は国の防衛や災害救助であり、野生動物の駆除を常態化させることは避けるべきであると考えられます。ここで問われるべきは、このような非常事態を招いた根本的な「責任」はどこにあるのかということです。その理由は、前述の通り、クマが人里に降りてくるのは人間の政策的な失策、すなわち無計画なメガソーラー建設やエサ場の破壊が原因です。少なくとも、環境大臣としてメガソーラー推進を主導した小泉進次郎氏には、これまでの政策の結果として国民の安全が脅かされ、自衛隊まで動員される事態になったことに対して、説明責任と再発防止策を講じる責任があります。そのため、これが出来れば、将来的に同様の問題が発生しないよう、政策の検証と修正が不可欠です。
熊の駆除で鹿の大繁殖 山は死ぬ懸念
そしてもう一つは、クマの大量駆除が進むことで、将来的に「シカの大繁殖」を引き起こし、日本の山がさらに荒廃するという深刻な懸念があることです。その理由は、クマはシカの幼獣や衰弱した個体を捕食することで、シカの個体数を自然の力で調整する本来は重要な役割を果たしているからです。ここでクマが減り過ぎてしまうと、シカの天敵がいなくなり、シカが爆発的に増加してしまいます。こうして増えたシカは、山の低木の葉や樹皮を食べ尽くし、その結果、森林の植生が破壊され、森林の下層植生が失われます。これを放置すると、地表がむき出しになり、保水力が低下し、土砂崩れなどの自然災害を引き起こしやすくなるという悪循環に陥ります。つまり、クマの駆除は、一時的に人里の安全を確保できるかもしれませんが、長期的には山全体、ひいては私たちの生活環境を「死なせる」ことにつながりかねません。このような理由から、クマの問題は単なる人身被害対策ではなく、生態系全体のバランスを考慮した、持続可能で複雑な課題として取り組む必要があります。
熊の出没原因とメガソーラー政策の失策総括
- 秋田県知事が「もう限界を超えている」と発言するほどクマ出没問題は深刻化している
- クマ被害の根本原因は、個体数増加ではなく人間による生息環境の急激な変化である
- 大規模メガソーラー建設のための森林伐採がクマの住居とエサ場を直接破壊している
- 建設業者による環境アセスメントは形式的になり、生態系への配慮が不足している
- 重機の騒音やフェンス設置がクマの行動範囲を分断し、人里へのルートを選ばせている
- メガソーラー敷地内での除草剤使用が、クマの食料源である草や小動物を枯渇させている
- 食料不足によりクマが人里の柿や栗に依存し、人間への警戒心を失いつつある
- 藤村晃子氏は10年前からクマ被害が「環境破壊の問題」であると警鐘を鳴らし続けていた
- 現在の悲劇は、長期間にわたる人間の「間違った政策」と警告の無視の結果である
- 小泉進次郎氏の環境大臣時代のメガソーラー急速拡大政策が問題の主因と指摘されている
- 環境保護を担う環境省が、規制緩和で大規模な森林伐採を事実上容認したのが最大の失策だ
- 「神奈川四毒」の政策が地方の生態系を「消化不良」にしたと批判されている
- クマ駆除という対症療法ではなく、根本原因であるメガソーラー政策の是非を問うべきである
- 人里へのクマ出没を招いた責任は、クマではなく無秩序な開発を推進した政策決定者にある
- クマの大量駆除は、シカの天敵を失わせ、将来的にはシカの異常繁殖による山の荒廃を招く懸念がある

