「映画『WHO?』はどこで見れるの?」そう思ってこの記事にたどり着いたあなたへ。
この映画は、2024年9月28日に東京・有明で行われた大規模なデモをきっかけに、コロナ禍の裏側を描いたドキュメンタリーです。
なるせゆうせい監督が、なぜこのデリケートなテーマを扱う決断をしたのか、その制作背景には深い思いが込められています。
この記事では、映画『WHO?』のあらすじや、井上正康氏、林千勝氏をはじめとする主要キャスト(出演者)がどのような熱い思いでこの作品に参加したのかを詳しくご紹介します。
さらに、気になる上映館や今後の公開予定、そして制作費の回収状況やDVD・ブルーレイの販売時期、自主上映という独自の広がりについても解説。
類似作品である『ヒポクラテスの盲点』との違いにも触れながら、この映画がどのように表現の自由を守るための応援となっているのかをお伝えします。
この記事のポイント
- 映画『WHO?』のあらすじや内容、主要な出演者について
- 映画が作られた背景や監督の思い、制作を決意した理由について
- 劇場での上映状況、今後の公開予定、自主上映という独自の広がりについて
- 制作費の回収状況やDVD・ブルーレイの販売予定、表現の自由を守るための活動について
映画『WHO?』の上映館と公開日は?
映画『WHO?』のあらすじ
映画『WHO?』は、コロナ禍の社会を多角的に捉えたドキュメンタリー作品です。
この映画の始まりは、2024年9月28日に東京・有明で行われた大規模なデモに焦点を当てています。
横断幕やプラカードには、政府が推奨するワクチン(と称する遺伝子製剤)やWHOに対する痛烈な批判が記されていました。
しかし、この大規模なデモは、メディアによってほとんど報道されることがありませんでした。
作中では、このデモに参加した人々にインタビューを行い、彼らがなぜ声を上げるようになったのか、何に問題を提起しているのかを深く掘り下げていきます。
単なるデモの様子を追うだけでなく、コロナ禍の裏側で何が起こっていたのか、真実なのか陰謀なのかという問いを観客に投げかける構成となっています。
大阪市立大学名誉教授の井上正康氏をはじめ、衆議院議員の原口一博氏、ITビジネスアナリストの深田萌絵氏など、多岐にわたる分野の専門家やジャーナリスト、そしてデモ参加者の視点から、未だ解決されていない問題を浮き彫りにします。
この映画は、言論弾圧によって多くの情報が隠蔽されてきた時代に、あえて真実を追求しようとする監督の強い意志が込められています。
なるせゆうせい監督が映画を作った背景
映画『WHO?』の監督、なるせゆうせい氏は、これまで社会課題をテーマにした青春映画を何本か手掛けてきました。
しかし、今回の作品はこれまでの作風とは異なり、ドキュメンタリー映画という形で制作されました。
監督は、自身がこのテーマを扱うことについて当初は大きなためらいがあったことを明かしています。
この問題は非常にデリケートであり、強い反発や批判が予想されるため、安易に手を出せるものではないと考えていたようです。
加えて、もし完成したとしても、このテーマを扱う作品を上映してくれる映画館が果たして存在するのかという懸念も抱いていました。
また、制作から公開に至るまで、批判の矢面に立つのは間違いなく自分自身であるという覚悟も求められました。
それでも、この映画の制作を決意したのは、井上正康氏や林千勝氏といった識者たちから直接依頼を受けたことが大きなきっかけとなりました。
監督は、この依頼を「一つの運命」として捉え、自らがこの問題に向き合う使命があると感じたようです。
このように、監督が自らの意思だけで始めたのではなく、周囲からの熱い思いに応える形で、この重要なプロジェクトがスタートしました。
なぜこの映画を制作する決断をしたのか
なるせゆうせい監督がこの映画の制作を決断した背景には、単純なビジネス的な判断を超えた、深い葛藤と責任感が存在しました。
監督はインタビューの中で、リスクを天秤にかけた結果だと語っています。
一つは、この映画を制作して批判や困難に直面するリスクです。もう一つは、このテーマから目を背けることで、将来さらに大きな問題が起こるかもしれないというリスクでした。
監督は後者のリスクの方が、より深刻だと考えました。このまま放置してしまえば、社会がさらに悪い方向へ進んでしまうのではないかという強い危機感を感じたのです。
この決断には、制作を依頼した人々や、声を上げようとしながらも埋もれてしまう人々の思いを代弁するという役割も含まれていました。
監督は、通常であれば2、3年かかる映画制作の期間を大幅に短縮し、可能な限り迅速に作品を完成させました。
これは、この問題が今すぐにでも多くの人々に知られるべきだと強く感じていたためです。
監督の切迫感と情熱が、作品のスピード感にも現れており、非常にタイムリーな内容となっています。
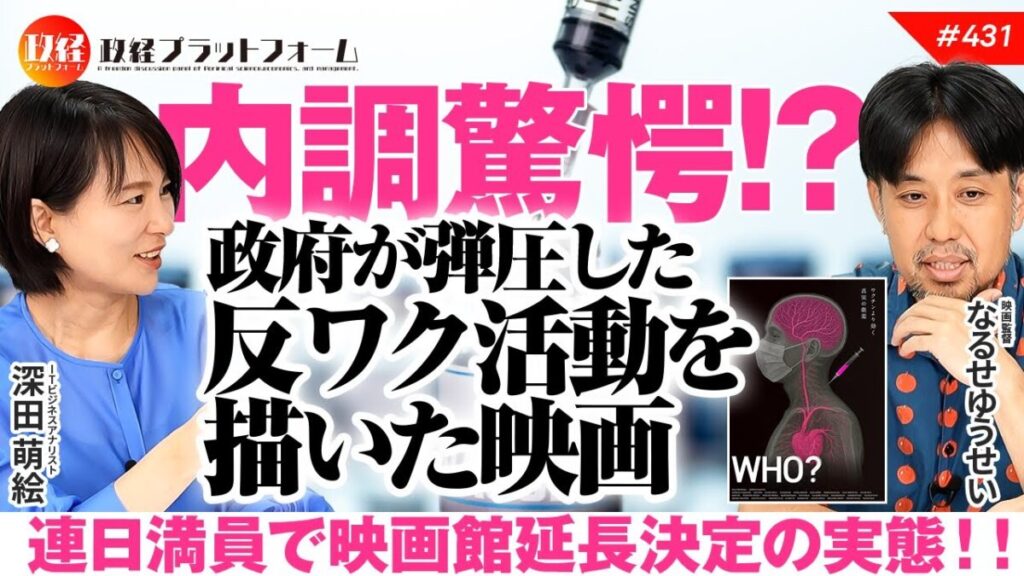
上映館と今後の公開予定
映画『WHO?』は、2025年8月16日にMorc阿佐ヶ谷で公開されて以降、全国各地の単館系映画館で上映されています。
大手シネコンでは、このテーマを扱う作品が上映されることは難しいのが現状です。
そのため、監督や制作スタッフは、一つひとつの映画館に直接連絡を取り、上映を依頼しています。
この配給方法は非常に手間がかかりますが、観客の声が直接反映されるというメリットもあります。
長崎での上映は、一度は劇場に断られてしまいましたが、地元の議員や市民が「ぜひ上映してほしい」と劇場に働きかけた結果、上映が実現しました。
これは、観客一人ひとりの行動が、作品の運命を変え得ることを示す象徴的なエピソードです。
公開から2週間で連日満席が続き、一部の劇場では上映期間の延長が決定するなど、口コミによって動員が広がっています。
DVDやブルーレイの販売、そして自主上映会の開催も、制作費の回収と作品をより多くの人に届けるために重要な役割を担っています。
具体的な上映スケジュールやチケット情報は、公式サイトで確認することができます。
劇場公開情報
| 都道府県 | 劇場名 | 公開日 | 上映時間 | 電話番号 |
| 東京都 | Morc阿佐ヶ谷 | 8月16日〜2週間<b9月19日〜 無期限再上映決定 | 8/16(土)〜8/21(木) 10:30〜 8/22(金)〜8/28(木) 10:20〜 | 03-5327-3725 |
| 兵庫県 | あいめっせホール・イーグレ姫路 | 8月30日 | 13:00 | 050-5468-5015 |
| 東京都 | シネマハウス大塚 | 8月31日~9月5日 9月9日(追加上映) | 8月31日 11:30/15:00/18:30 9月1日~9月5日 19:00 | 080-8628-4402 |
| 大阪府 | 新世界ZAZA | 9月6日~9月7日 | 11:30/15:00/18:30 | 080-8628-4402 |
| 埼玉県 | OttO | 9月10日〜11日 | 15:20 | 080-8628-4402 |
| 神奈川県 | ジャックアンドベティー | 9月13日〜2週間 | 9月13(土)〜19(金)14:20~16:10 9月20日〜26日(金)14:10~16:00 | 045-243-9800 |
| 長崎県 | セントラル劇場 | 9月19日〜1週間 | 13:40/19:00 | 095-823-0900 |
| 埼玉県 | 七ツ梅精米所ホール(精米所煉瓦ホール) | 9月20日~9月21日 | 9月20日(土)13:30 9月21日(日)11:00/13:30 | 080-8628-4402 |
| 兵庫県 | 洲本オリオン | 9月23日〜 | 15:20 ※9/27(土)・9/28(日)のみ16:00 | 0799-22-0265 |
| 大阪府 | シアターセブン | 9月27日 | 11:35/14:25 | 080-8628-4402 |
| 長野県 | 千石劇場 | 10月3日~2週間 | 未定 | 026-226-7665 |
| 群馬県 | 前橋シネマハウス | 10月4日〜10月10日10月18日〜10月24日(※10月11日~10月17日の1週間は休館日となります。) | 未定 | 027-212-9127 |
| 愛知県 | シネマスコーレ | 10月20日~23日 | 18:30 | 052-452-6036 |
| 北海道 | サツゲキ | 10月25日 | 16時10分~ | 080-8628-4402 |
| 岡山県 | 岡山メルパ | 10月31日~2週間 | 未定 | 086-221-0122 |
今後の詳細は公式HPでご確認ください。
主要キャスト(出演者)を紹介
映画『WHO?』には、さまざまな分野から多くの著名人が出演しています。
この映画の制作を依頼した中心人物である、大阪市立大学名誉教授の井上正康氏や近現代史研究家の林千勝氏は、コロナ禍でメディアが伝えない情報や専門家としての見解を語る役割を担っています。
また、衆議院議員の原口一博氏は政治の視点から、ごぼうの党代表の奥野卓志氏やITビジネスアナリストの深田萌絵氏はそれぞれの専門分野から独自の分析を展開。
特に深田氏は、ITの観点からパンデミックと監視システムの関連性を指摘するなど、新たな視点を提供しています。
さらに、名古屋大学名誉教授の小島勢二氏や高知大学名誉教授の佐野栄紀氏、そして医師の内海聡氏といった専門家も参加し、専門的な知見からワクチンの安全性や問題点を解説しています。
ちなみに、内海聡氏といえば、2021年に著作『医師が教える新型コロナワクチンの正体』の車内広告が、東京メトロによって撤去されたことで話題になりました。
東京メトロは「マスクにはウイルスを防ぐ効果がない」という書籍内の記述が、同社のマスク着用案内に反し、利用客に誤解を与える可能性があると判断したようです。
その後、内海氏のSNSアカウントが凍結されるなど、コロナ禍における言論統制の一例として注目されました。
その他、国際ジャーナリストの堤未果氏や俳優の松尾貴史氏など、幅広いジャンルの人々がこの映画に出演しています。
これらの人々がそれぞれの立場から語ることで、一つの出来事を多角的に捉え、観客に深い洞察を与えています。
を紹介.jpg)
映画『WHO?』公開記念対談と林千勝氏のXアカウント凍結について

映画『WHO?』の公開に先立ち、井上正康氏と林千勝氏の対談が公開されました。この対談は、映画の核となる部分を深く理解する上で非常に重要な内容となっています。
対談の中で、井上氏は、大半の国民、そして多くの医師ですらワクチンの危険性について十分に理解していない現状に警鐘を鳴らしました。多くの人が、ワクチンによる副作用や健康被害を、ワクチンと結びつけて認識できていないことに懸念を表明しています。
一方、林氏は、財務省前などで行われた数万人規模のデモが大手メディアで一切報道されなかったことに触れ、これが「国民が置かれている情報の壁」であると指摘しました。
かつてであれば、数千人規模のデモであってもメディアが取り上げていたにもかかわらず、何万人もの国民が集まったデモが黙殺されたことは、現在の言論空間の異常さを示していると語っています。
両氏は、これから言論弾圧がさらに厳しくなる可能性があると予測し、そのような状況において、映像の力で真実を広く国民に伝えることの重要性を強調しました。
この映画が、国民自らが自分たちの命を守るための情報を得る「武器」となり、自分で考えて行動するきっかけになることを強く期待しています。
林千勝氏のXアカウント凍結
対談が公開された後、林千勝氏のXアカウントが凍結されたことが明らかになりました。
この凍結は、Xが自由な言論空間であるという認識が揺らいでいることを示しています。
みのり先生の診療室ブログによると、言論弾圧は昨年12月に岩屋外務大臣が中国と交わした密約をきっかけに始まり、4月1日の「情報プラットフォームサービス提供者等による流通情報対応義務法(通称:情プラ法)」の施行によってさらに顕著になったとされています。
また、参議院選挙中に自民党の平井卓也議員が「投稿を消し込みにいってる」と発言したことから、政府が不都合な情報を削除していることが示唆されました。
林氏のアカウントが凍結された理由については、9月23日(火・祝)に予定されているWHO脱退デモの拡散を阻止するためではないか、との見方が示されています。
これらの出来事は、対談で井上氏と林氏が指摘した「言論弾圧の厳格化」と「情報の壁」が現実のものであることを裏付ける形となりました。
連絡なく凍結解除となりました。
— 林 千勝 Hayashi Chikatsu (@ChikatsuHayashi) September 12, 2025
イーロンに声が届いたのだろうか。
皆様に感謝です。
9.23 国民運動 @新宿 戸山公園 10時集合!
ひるまず、たゆまず。
オールジャパンで命を守る! pic.twitter.com/5jCA4mAKwQ
映画『WHO?』はどこで見れる?
制作費の回収はできている?
映画『WHO?』は、クラウドファンディングを通じて多くの人々の支援によって制作されました。
そのため、エンドロールには支援者たちの名前が多数掲載されています。
しかし、監督はインタビューの中で、公開から2週間が経過した時点でも、制作費の回収にはまだ至っていないことを率直に語っています。
映画業界の構造として、劇場公開の収入だけで制作費を回収するのは非常に難しいのが現実です。
映画館でのチケット収入は、多くの場合、劇場側と配給側で分けられるため、制作サイドに入ってくる金額はチケット代の半分程度に過ぎません。
これまでのインディペンデント映画の多くは、劇場公開だけでは赤字となり、DVDやブルーレイの販売、有料配信、そして自主上映会などで費用を賄うことが一般的です。
この映画も例外ではなく、監督は「まだまだ先は長い長期戦」であると述べています。
連日満席が続いていたとはいえ、それが直接的に制作費の回収につながるわけではありません。
しかし、多くの観客が劇場に足を運んでいることは、今後の上映延長や二次利用に向けた追い風となっています。
自主上映という選択肢
映画『WHO?』をより多くの人に届ける上で、自主上映会は非常に重要な役割を担っています。
大手シネコンでの上映が難しいこの種の作品にとって、有志が会場を借りて上映を行う自主上映会は、作品を観客に届けるための有効な手段です。
監督は、この映画が「長期戦」になると語っており、劇場公開だけでなく、様々な方法で作品を流通させる必要があると考えています。
自主上映会は、作品を支持する人々が主体となって開催されるため、熱意が伝わりやすく、口コミでの広がりも期待できます。
長崎での上映が市民の声で実現したように、自主上映会もまた、観客や支援者の行動が直接的に作品の命運を左右するケースと言えるでしょう。
このような草の根の活動が活発になればなるほど、映画はより多くの人々の目に触れる機会が増えます。
監督自身も、地方の劇場に直接電話をかけて上映交渉を行うなど、自主上映を促すような活動に積極的に関わっています。
このような働きかけは、劇場側が観客のニーズを把握し、上映を決定する上で重要な判断材料となります。
DVD・ブルーレイの販売はいつから?
映画『WHO?』のDVDおよびブルーレイの販売時期については、現時点ではまだ具体的な発表はありません。
インディペンデント映画のビジネスモデルを考えると、劇場公開の収入だけで制作費を回収するのは非常に困難です。
そのため、監督や制作陣は、劇場での上映終了後、DVDやブルーレイの販売、そして有料配信サービスなどを通じて、長期的に収益を上げていくことを計画しています。
これらの二次利用が、映画をより多くの人々に届けるための重要な手段となります。
また、クラウドファンディングで制作費を支援した人々の存在も、この作品の今後の展開に大きく影響するでしょう。
彼らは、作品が多くの人に届くことを望んでおり、そのための媒体として物理的なディスクや配信サービスが不可欠となります。
劇場に足を運べない人々にとっても、ディスクの販売は作品に触れる貴重な機会となります。
監督は、作品を多くの人に届けることを最優先に考えているため、劇場公開の動向を見ながら、最適なタイミングで販売や配信に関する情報を発表すると思われます。
『ヒポクラテスの盲点』との違い
映画『WHO?』と同じ時期に公開されたドキュメンタリー映画『ヒポクラテスの盲点』は、同様のテーマを扱っているものの、そのアプローチには大きな違いがあります。
なるせゆうせい監督は、自身の作品が全世界的な視点、つまり「グローバリストたちにも含めてのそのコロナ禍のこの過程も含めての話」であると述べています。
これは、単に被害者の声を拾うだけでなく、パンデミックがどのように計画され、実行されたのかという構造的な問題にまで切り込んでいることを示唆しています。
一方で、『ヒポクラテスの盲点』は、主にワクチン接種による被害者や遺族の苦しみに焦点を当てているとされています。
それぞれの作品が異なる視点を持っているため、どちらが良い・悪いというわけではありません。
しかし、その制作体制には大きな違いが見られます。『ヒポクラテスの盲点』は、テレビ番組の制作会社が手掛けており、予算や配給において比較的スムーズに進んでいると見られています。
それに対し、『WHO?』は監督自身の強い信念と草の根の支援によって制作された、まさに独立系の作品です。
同じテーマを扱いながらも、その成り立ちや焦点が異なる両作品は、それぞれの方法で人々に問題提起をしています。
あわせて読みたい
>>【2025年公開】映画 ヒポクラテスの盲点が問うコロナ禍の闇
『WHO?』の世界観を深掘り!『コロナは概念』とは何か
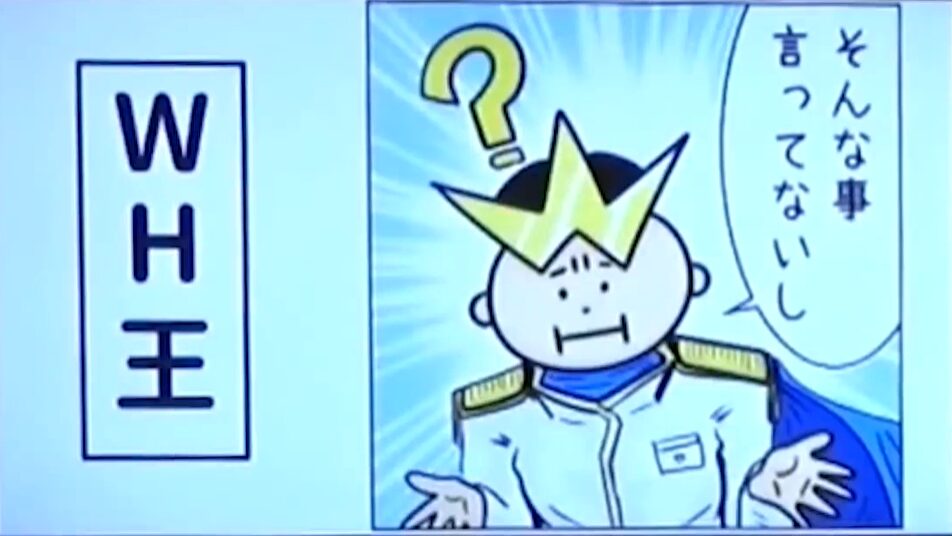
「コロナは概念」という言葉をご存知でしょうか。
これは、コロナ禍を社会の矛盾として鋭く風刺した作品で、当時はYouTubeで公開されていましたが、現在は削除され、一部の動画サイトにしか残っていません。
この動画の世界観を基にした漫画『コロナは概念☆プランデミック』が出版されており、クスッと笑える4コマ漫画で、当時の社会状況を面白く、わかりやすく描いています。
この書籍は、コロナ騒動を軸にした風刺漫画で、「コロナ王」や「インフル先輩」といったユニークなキャラクターが登場します。
作中では「PCR教団の台頭」や「気まぐれWH王」といった、当時の社会状況を風刺したテーマが盛り込まれており、読者は楽しみながらも、深く考えさせられる内容となっています。
この漫画は、ドキュメンタリー映画『WHO?』が真実を追究する一方で、風刺という異なる角度から同じテーマに光を当てています。
社会の矛盾や権威への疑問を、ユーモアを交えて表現することで、多くの人々に共感と癒しを与えています。
表現の自由を守るための応援
この映画の制作と公開は、現代社会における表現の自由と、それに伴う言論弾圧の問題を浮き彫りにしています。
監督はインタビューの中で、YouTubeなどのプラットフォームでは、このテーマを扱うとアカウント凍結のリスクがあると語っています。
実際に、多くのジャーナリストや医師たちが、従来のメディアとは異なる形で情報を発信しようとした際に、様々な規制や検閲に直面してきました。
このような状況下で、映画という媒体は、検閲されにくい表現の場として機能します。映画館での上映は、監督が「言論弾圧されずにすむ」と考える、数少ない手段の一つです。
また、この映画は、多くの支援者によるクラウドファンディングで成り立っています。
この支援は、単に制作費を賄うだけでなく、監督や出演者たちが直面するリスクを支えるためのものでもあります。
この映画を劇場で鑑賞したり、今後発売されるディスクを購入したりすることは、作り手への感謝を示すだけでなく、彼らが守ろうとしている表現の自由そのものを応援することにつながります。
観客一人ひとりの行動が、このような独立系作品の存続を支え、ひいては社会の健全な言論空間を守ることになるのです。
監督と出演者の熱い思い
映画『WHO?』は、なるせゆうせい監督と出演者たちの、この問題に対する並々ならぬ情熱によって生み出されました。
監督は、この作品を「生き物」のようだと表現しています。なぜなら、制作期間中も社会情勢が刻々と変化し、その変化に合わせて内容を調整する必要があったからです。
特に、トランプ氏の動向など、国際的なニュースが作品の方向性に影響を与えました。
監督は、常に最新の情報を反映させるため、公開直前まで編集作業を続けていました。
また、この映画には、各分野の第一線で活躍する人々が、自らの立場やキャリアをかけて出演しています。
彼らは、メディアが報道しない真実を伝えるために、批判や非難を覚悟してカメラの前に立ちました。
これは、単なる出演依頼に応じただけではなく、彼らがこの問題の重要性を深く認識し、多くの人々に真実を伝えたいという強い使命感を持っていたからに他なりません。
監督自身も、地方の劇場に直接電話をかけて上映交渉を行うなど、作品を一人でも多くの人に届けるために、驚くほどの熱意と行動力を示しています。
この映画は、単なるドキュメンタリーではなく、真実を追い求める人々の熱い思いの結晶なのです。
映画『WHO?』はどこで見れる?上映館と公開情報まとめ
- コロナ禍の社会を多角的に描いたドキュメンタリー映画
- 2024年9月28日の東京・有明での大規模デモがテーマ
- メディアが報道しなかったデモの参加者たちにインタビューを実施
- 監督は社会課題を扱ってきたなるせゆうせい
- 当初は制作にためらいがあったが、識者からの依頼を受け決断した
- 制作費はクラウドファンディングで賄われた
- 通常より短い期間で完成させ、タイムリーな内容となっている
- 出演者は井上正康氏や原口一博氏など多岐にわたる
- 深田萌絵氏はパンデミックと監視システムの関係性を指摘した
- 林千勝氏はメディアが黙殺する「情報の壁」に言及した
- 2025年8月16日からMorc阿佐ヶ谷で公開された
- 大手シネコンでの上映は難しく、単館系映画館で公開されている
- 観客や支援者の声が上映延長や新規上映に繋がっている
- 制作費の回収はまだできておらず、長期戦となる
- DVD・ブルーレイの販売や自主上映会が今後の重要な役割を担う



